
司馬遼太郎は好きで以前からよく読んでいる。
あの独特のカメラ位置から語られる物語と解説、余談を一度味わったら、
他の歴史小説がどうしても味気なくなってしまう。
これからも司馬遼太郎は読んでいくだろう。
しかし、これまで通りにただ漫然と「司馬史観」を楽しむのではだめだ。
俺は前回個人憲法を策定した。以下の内容である。
第1条 俺=人=仏
第2条 この世の全ては兵法
第3条 富貴である
この観点から司馬遼太郎、もとい彼の作品を見つめ直していく。
国民文学
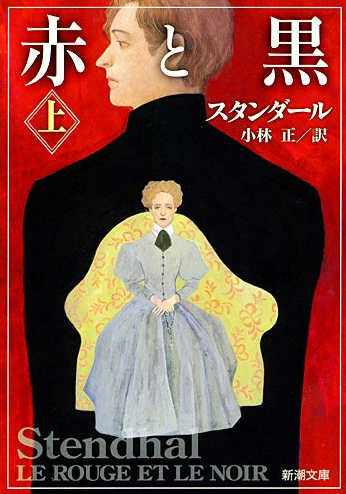
彼は日本の「国民的作家」である。その他司馬遼太郎の詳細はWikipediaに譲る。
どこで見たか忘れたが、「国民文学」という概念があるそうで、
フランスの場合は「赤と黒」
イギリスの場合は「リア王」
ロシアの場合は「戦争と平和」
なんだとか(うろ覚えんなので作品は違うかもしれないが、どちらにせよ同レベルの名作が据えられる)。
これが、日本の場合は「坂の上の雲」なのだそう。
「雪国」や「金閣寺」、「斜陽」ではない。
広辞苑で「国民文学」は以下のように定義されている。
①特に近代になって作られた一国の国民の特性や文化のあらわれた独特の文学。
②国民の独立・統一・社会的進歩などの課題を意識し、国民の各層に広く読まれる文学。
「雪国」「金閣寺」「斜陽」はこの条件に当てはまらないということになる。
「雪国」はどうか知らないが「金閣寺」「斜陽」はベストセラーだったそうだがそれでは駄目らしい。
西洋の方のチョイスも調べていないので事情はわからないが、
なぜ「坂の上の雲」がこれに当てはまるかはわかる。
「坂の上の雲」は新聞で連載されていた。
司馬遼太郎のヒット作の多くは新聞連載だ。
「金閣寺」も「斜陽」も現代から見れば空前の大ヒットといっていいが、
人の目に触れたという意味では「坂の上の雲」に及ばないだろう。
国家の成立

無論ヒットだけが理由ではないだろう。
それだけならほかの大衆小説も国民文学になりえる。
国民文学の定義を見直してみると、
国民の情緒とかよりも、国家の歴史、特に成立史が重要のようだ。
「赤と黒」はナポレオン戦争後の王政復古期の時代が舞台だ。
ジュリアン・ソレルという野心に燃える低い生まれの若者が、
立身のため軍人を目指したり、聖職者になったりして、最終的には身分違いの恋が原因で死刑になる。
死刑を免れることもできたが、それまで見てきた上流階級へ唾を吐くため、敢えて死刑を受け入れたのだった。
フランスは近代を通して共和政、帝政、王政と様々な政体を辿るが、
一貫して「赤と黒」は読まれ続けた。
それはなぜか。そもそも近代フランスは、上の階級を打倒して誕生した。
以後の政体も変容も、ある意味その下剋上を延々と繰り返しているともいえる。
国家が辿った上流階級へ対抗史が、作中のソレルの生きざまと重なるのだ。
では、「日本」と「坂の上の雲」はどのように結びついているか。
それは「日露戦争」である。
近代フランスがフランス革命によって成立したのではなく、幾度の革命によってできたように、
近代日本は明治維新によって成立したのではなく、日露戦争の勝利で成立した。
フランス第一革命も明治維新も、あくまで土台でしかない。
よく考えれば当然の話で、これらは本来、前政権時代の一事件にすぎなかったはずだ。
フランス王国、江戸幕府の多くの構成員にとっては青天の霹靂で、その時点で国民の意識は介在しない。
彼らがそれを新国家と気づくのは、新しい為政者によって形作られていた曖昧な境界線が外部と接触した時だ。
その後から国家の物語は始まる。
フランスの場合は革命後わずか数年でオーストリアと戦端が開いたので覚醒は早かった。
日本の場合、明治維新後は内戦はあれど対外戦は暫くなかったため初動は随分と遅れた。
日清戦争でようやく日本人は国家というものを認識し、日露戦争でそれは完成した。
「庶民が国家というものにはじめて参加しえた集団的感動の時代」
司馬遼太郎は明治維新から日露戦争までの三十余年をこう評している。
果たしてそうだろうか。
あったとしても、それはインテリ層のみで、大多数の農民で構成される新国民たちが同じように思っていたとは考えずらい。
当時のメディアは新聞がメインだ。
そして19世紀後半の日本の識字率は60%ほど。それも地域差が大変激しい。
これが90%台まで登るのは20世紀に入ってからである。
多くの国民が新聞を見る習慣ができて、初めて国家の認識が全国に広まった。
それまで無論伝聞では知っていただろうが、比較しなければ、その物事自体を知ることはできないものだ。
先進国=白人、そしてその白人国家であるロシアに勝利したことで、国民国家大日本帝国は完成を見た。
この流れを、「坂の上の雲」の作中人物達は、あからさまな程、というよりほぼそのままなぞっている。
歴史小説だから当たり前だが。「赤と黒」における上品な文学的隠喩はそこに一欠片もない。
ここから考えてみると、「雪国」「金閣寺」「斜陽」が国民文学たりえない理由がわかるだろう。
司馬遼太郎という作家

司馬遼太郎は作品を書く際、若い頃の自分へ手紙を書くつもりで書いていたそうだ。
昔の日本はこんなんじゃなかったんだぞ、と敗戦で落ち込んでいた自分へ語りかけていた。
このことからもわかるだろう。
司馬遼太郎作品は日本という「国家」が前提として成立しているのだ。
だからこそ彼の歴史小説は国民文学となり、そして現代でも読まれているのだ。
逆に言えば、彼の作品におけるよい人物とは「国家」からみたよい人物なのである。
彼らは以下いずれかの要素一つ以上を持つ。
- 近代的合理主義
- 近代的組織哲学
- 近代における世界勢力図拡大への可能性
こんなところだろうか。これらを持たない人物は「甘ったれ」だとかいわれたりする。
そんな彼にとって薩長の維新志士たちの多くは英雄である。
戦前の共産党の書記長を務め、戦後右翼に転じた田中清玄という男がいる。
会津藩家老の血を引いている彼は、司馬遼太郎を「私に言わせれば彼は薩長代表のようなもん」と評した。
別に例に挙げるまでもなかっただろうが。
なににせよ司馬遼太郎作品が他の歴史小説家たちのそれと比べ、
経営者やらから人気を博しているのはこういう理由があるのではないか。
司馬遼太郎から見た徳川家康
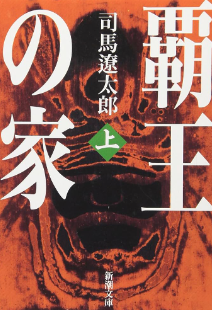
さてそんな国家の人(ちょっと言い過ぎからもしれない)である司馬遼太郎から見た徳川家康とはどんな人物だろうか。
「覇王の家」は徳川家康の生涯を追ったものだ。
特に特筆すべき点はなく、巷の徳川家康評と目立った剥離はない。
家康という、この気味わるいばかりに皮質の厚い、いわば被攻撃型の、かといってときにはたれよりもすさまじく
足をあげて攻撃へふみこむという一筋や二筋の縄で理解できにくい質のややこしさをつくりあげたのは、
ひとつにはむろん環境である。
複雑な環境を生き抜くために生まれた、後天的リアリスト。
人間の思考は、本来幻想的なものである。
人間は現実の中に生きながら、思考だけは幻想の霧の上につくりたがる生物であるとすれば、
現実的思考だけで思考をつくりあげることに努めているこの家康という男は、
そうであるがゆえに一種の超人なのかもしれなかった。妙な男であった。
特筆すべきは以下だ。
これは家康が信長から送られた季節外れの桃を、食中毒を恐れ食わなかったエピソードを引用して、彼を評したものである。
家康という人物は、日本の歴史に対し先覚的な事業をすこしも遺さなかったという点で、めずらしいほどの存在である。
この桃も食えないほどの慎重さが、彼を先覚者にしなかった。
司馬遼太郎が嫌う筆頭の人物として挙げられる山県有朋もまた、みんなでフグを食う中自分だけ食わなかった逸話がある。
思えば山県も家康同様、高杉、大村、西郷という異端児たちの後塵につきつつも、最後は新国家の舵取り役に収まった。
小説に取り上げられるような先覚者は、多少なりとも自己犠牲の精神がつきまとう。
そういう意味では自分を仏のように大切にし、自分以外のもの全てに疑いの目を向け、目の前にあるもので満足しようとする、
そんな信条をもっている俺などは英雄とは真逆なのだろう。
ただ司馬遼太郎は、彼をけなすだけではない。
しかし家康にはただ一つだけ先覚的要素がある、保健衛生の面である。
(中略)
しかしこれらのすべての衛生的教養はかれ個人の生存のためにのみ存在し、
かれが天下人になってからもそれを政治の場で公にせず、このためひょっとすると
かち得たかもしれない公衆衛生行政の先覚者という名誉を逸した。
もし家康が保険行政に力をいれていれば、という評価軸もまた近代的合理主義を礼賛する彼らしいものだ。
しかしこれまでのそれと異なるのは、対象が軍事や政治のそれではなく「衛生」である点だ。
「衛生」は近代国家の必須要件の一つではある。
しかしあくまで個人の「趣味」でしかないものを世間に広める家康ではなかった。
国家の人、あるいは
結局、司馬遼太郎は俺如きが語れるほど浅い男ではなかった。
右翼から見たらこれまで俺が書いた内容は左翼っぽく見え、逆に司馬遼太郎は右翼っぽく見えただろう。
だが司馬遼太郎はどちらでもない。どちらの要素も併せ持っているのだ。
だからこそある時叩かれる存在でもある。
右翼からは乃木叩きで叩かれ、
左翼からは封建主義的文化の擁護者と時にみられる。
右翼左翼というもの自体、近代の幕開けとともにうまれたものだから、近代国家の人である司馬遼太郎につきまとうのは必然なのだろう。
今後も司馬遼太郎は読んでいく。
結局彼という男がわからなかったが、それは国家というものがわからないからだろう。
彼の作品を読んでいくうちにわかるのかもしれない。
ここで個人憲法を改めて見返してみる。
第1条 俺=人=仏
第2条 この世の全ては兵法
第3条 富貴である
俺は仏だ。ほかの人も仏だ。仏を大切にするのは当然で、仏を守るのはまぁよいものだ。
国家はときに仏を守る。どちらかといえばそれは仏ではなく、文化だとか仏像だとかの側面が強いが、
まぁ結果的に守られているのでいいだろう。
この世の全ては兵法だと考えた場合、国家もまた兵法ということになる。
つまりは誰かの利益のために国家というものは存在しているということだ。
民主主義国家の場合、言葉面だけとるならば、国民の利益ために国家というものは存在していることになる。
富貴であるためには最低限の財産権が必要だ。持つ権利は当然として、捨てられる権利も必要だ。
これらを併せて考えると、少なくとも俺は共産主義国家や独裁主義国家には向かないようだ。
半面、そこまで突き詰めていないのでこの時点で断言はできないが、自由主義国家と俺の個人憲法はなじむ点が多い。
自分を仏のように大切にし、自分以外のもの全てに疑いの目を向け、目の前にあるもので満足する。
これがためには国家からの不干渉が必要不可欠だ。
突き詰めれば個人主義だ。そういえば司馬遼太郎の作品の主役たちは、みな個人主義的側面を持つ。
やはり司馬遼太郎はわからない。
一つだけ確実なのは、彼は人だけがもつ夢やら大義やらを、国家をはじめとする集団が持つのを嫌った。
主人公は、あるいはこの時代の小さな日本ということになるかもしれないが、
ともかくも、われわれは三人の人物の後を追わねばならない。
「あるいは」「かもしれないが」「ともかくも」
この坂の上の雲の冒頭、ここに彼の思想の根幹があるのかもしれない。
ところで「坂の上の雲」はなぜ「坂の上の雲」なのだろうか。
語呂がいいだけかもしれない。
「坂の上の太陽」や「坂の上の月」、なんなら「坂の上の飛行機」でもよかったはずであろう。
まぁ、語呂だろう。